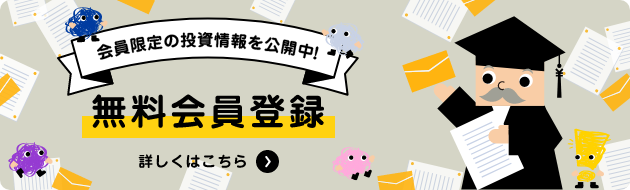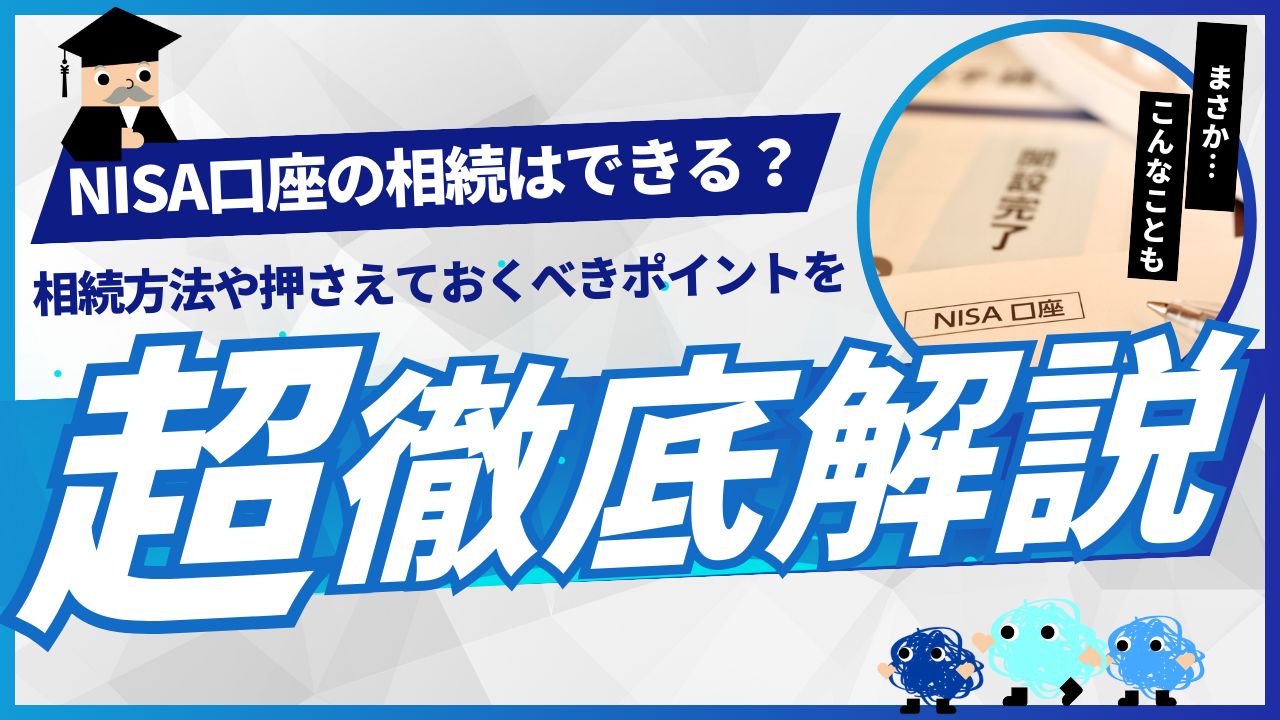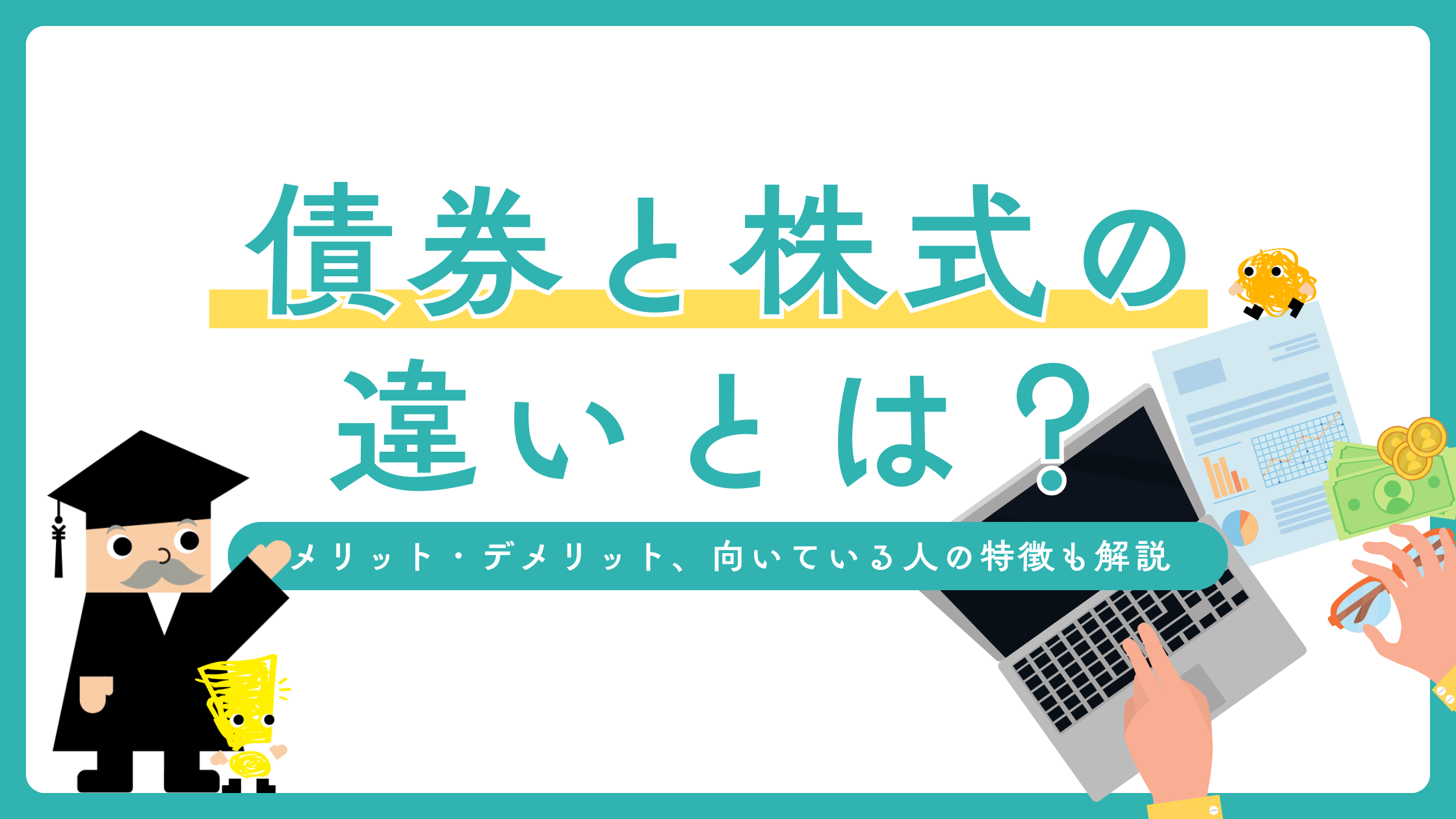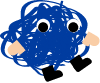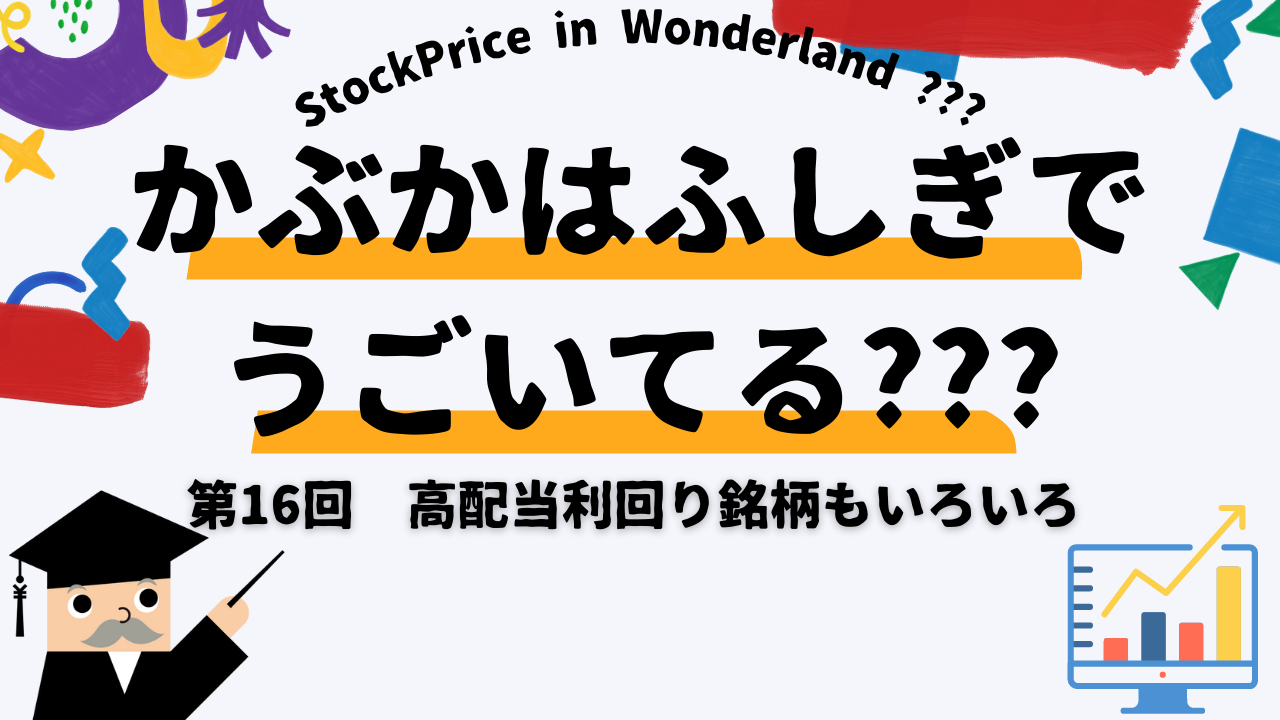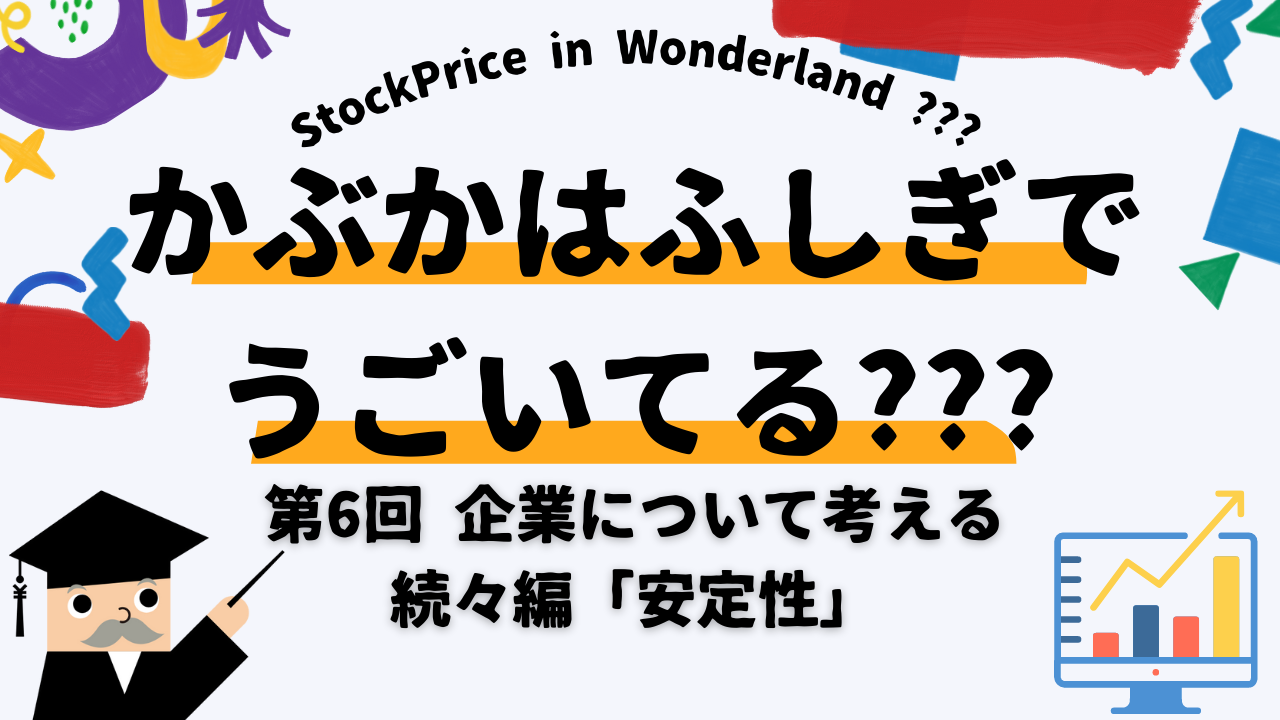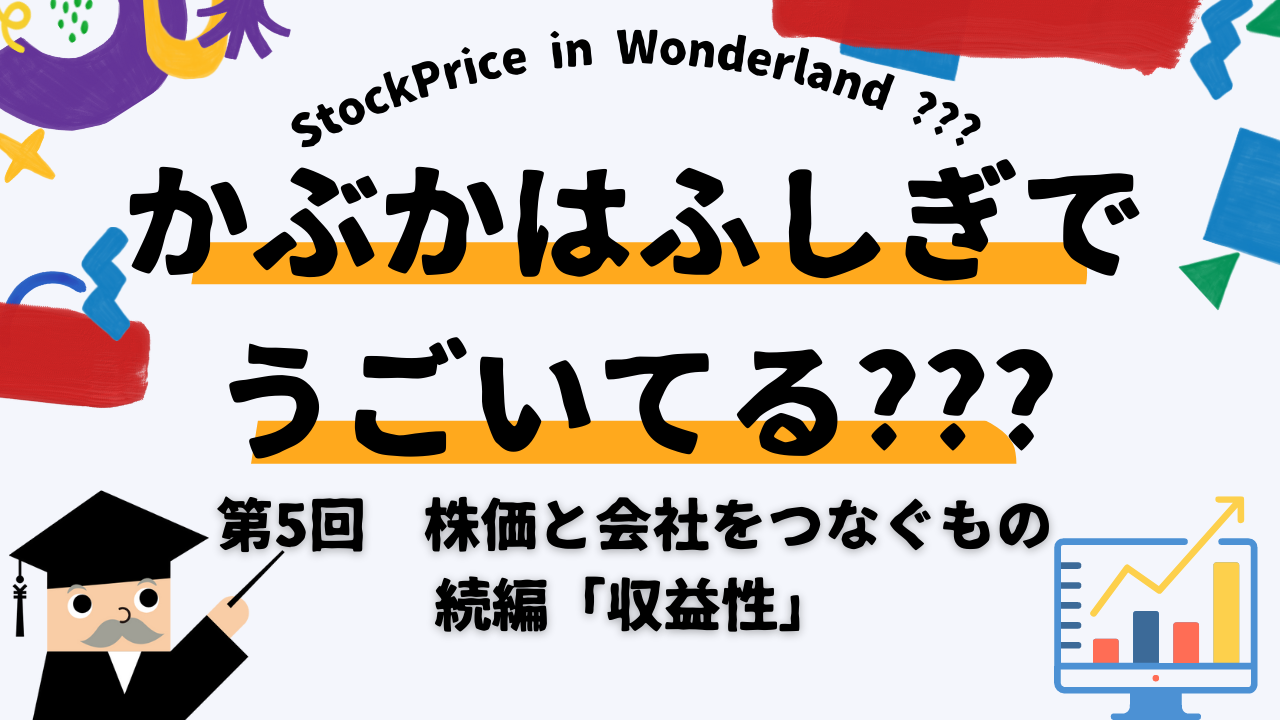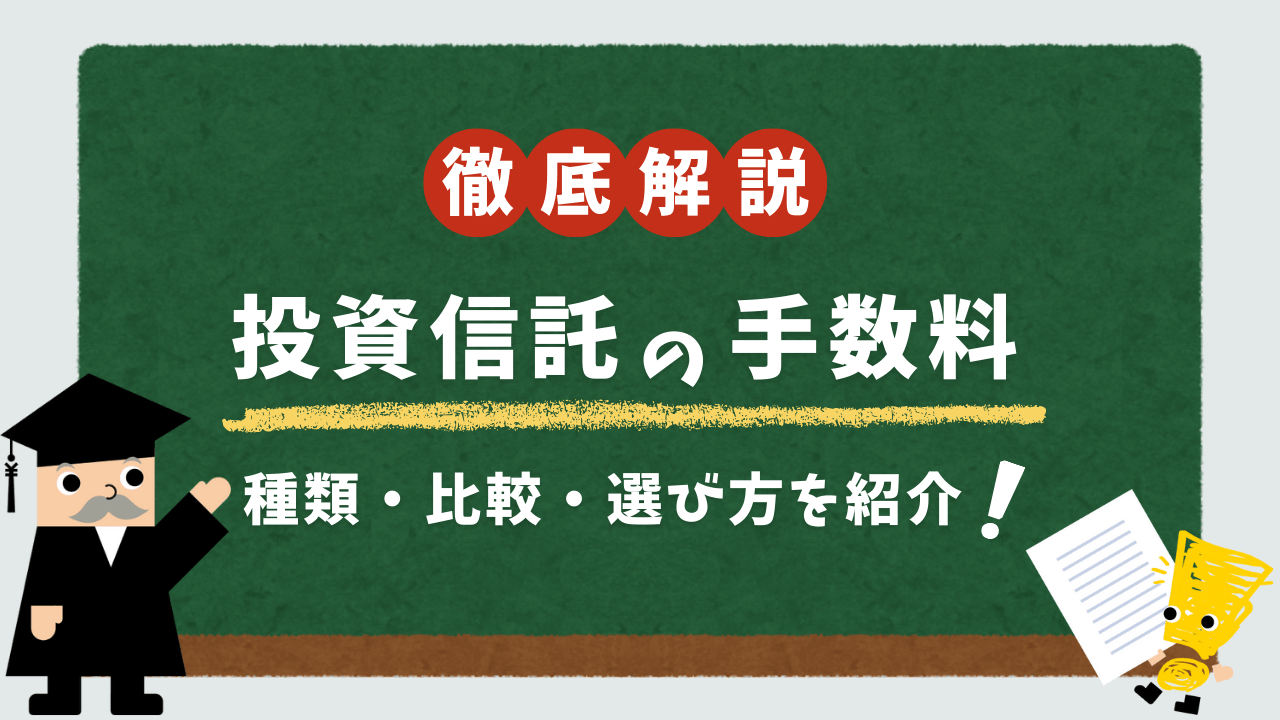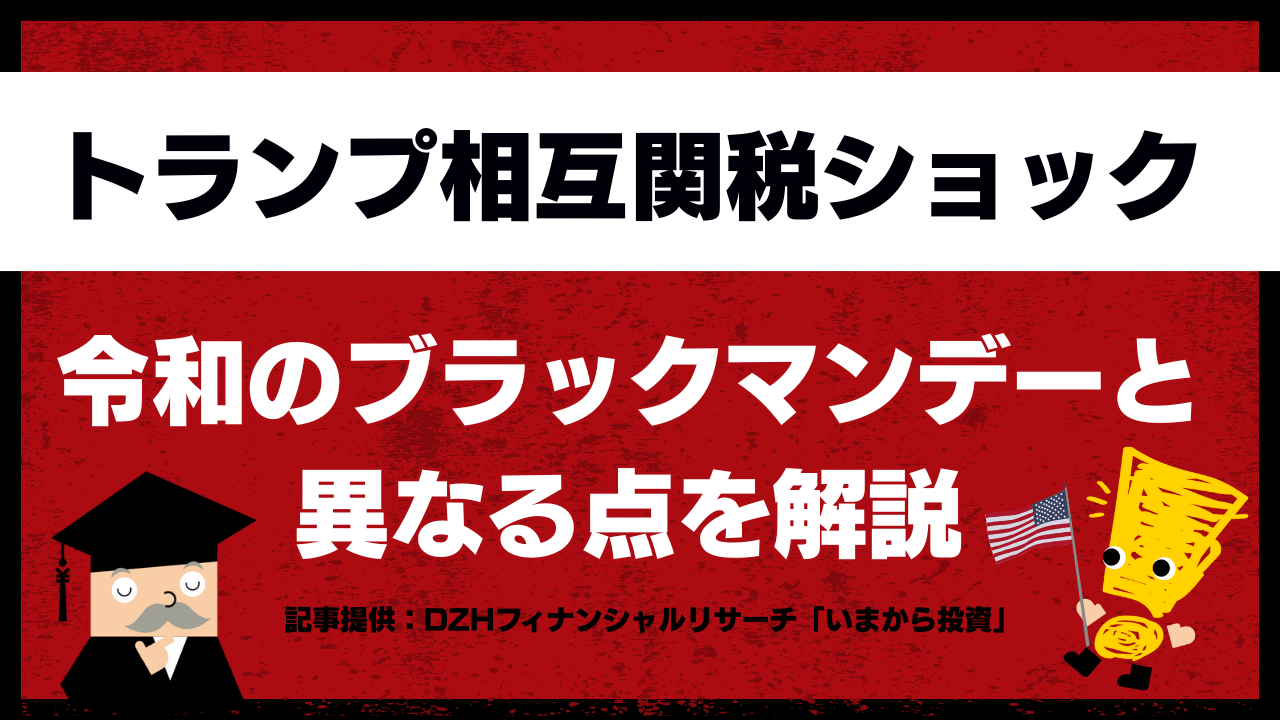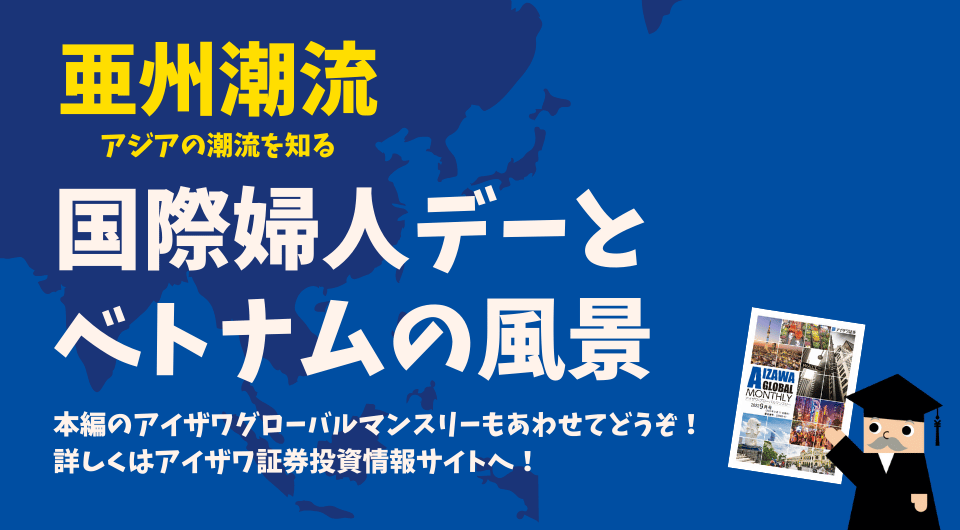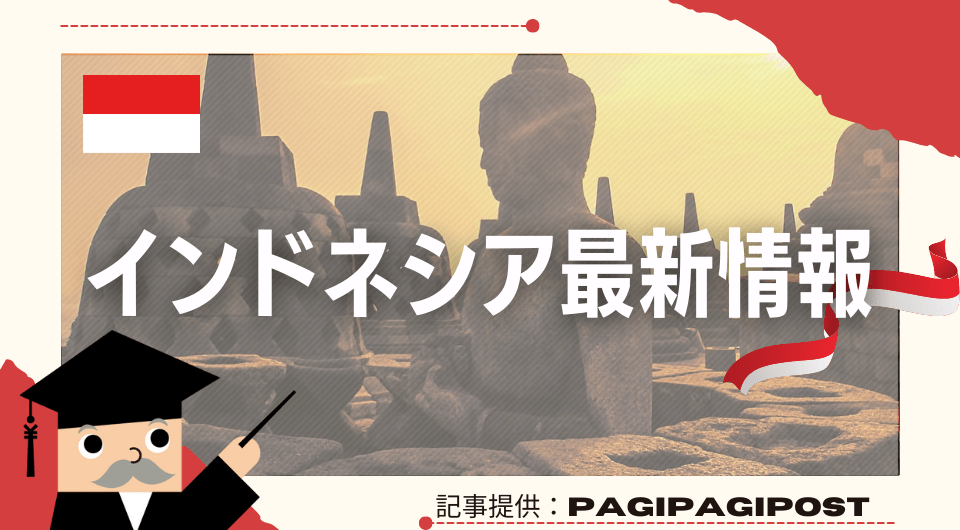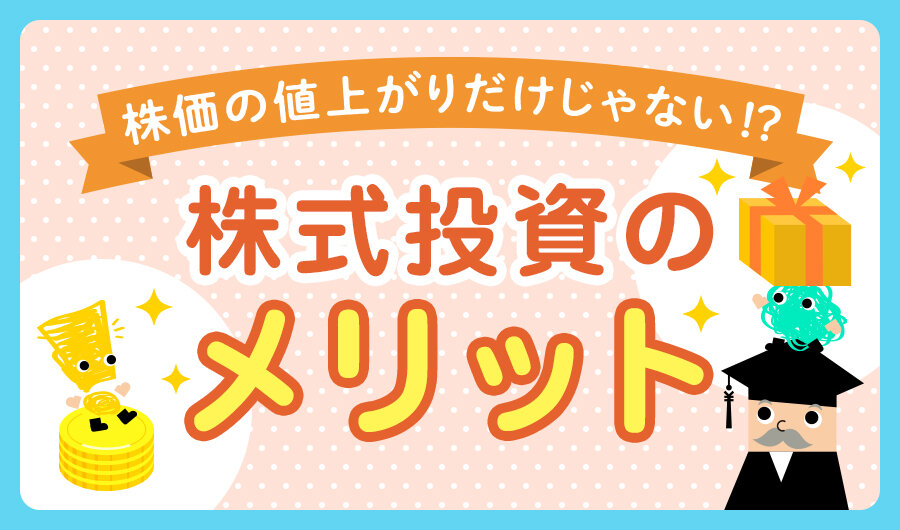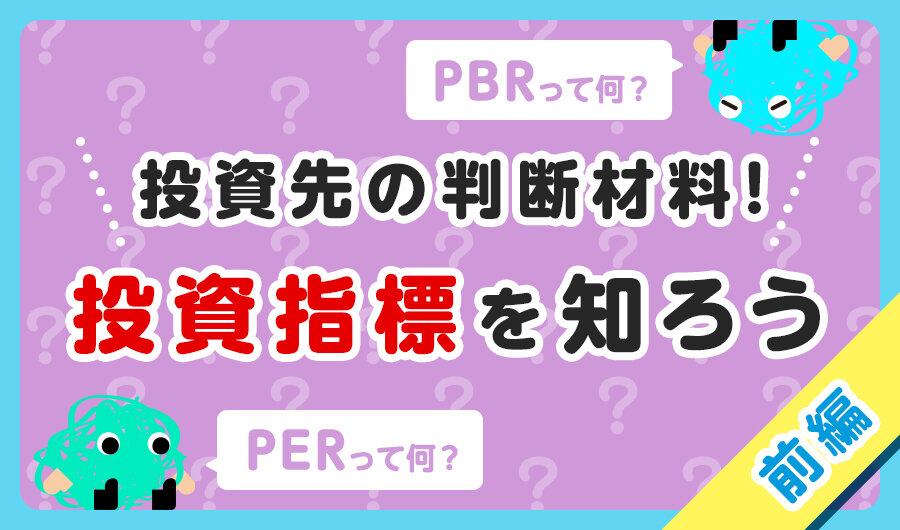特定口座と一般口座の違いとは?口座の選び方も紹介
2025.04.24 (木)
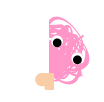
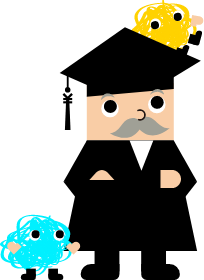

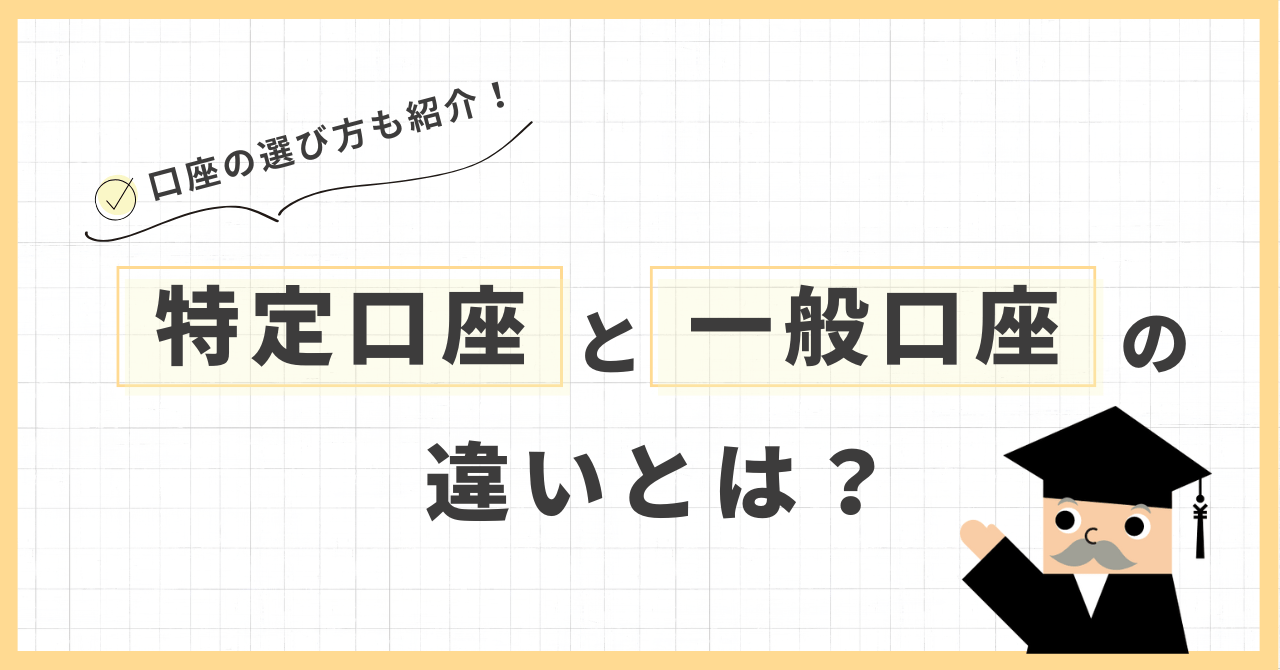
特定口座と一般口座は、株式や投資信託などを取り扱う証券会社で投資を始める際に選択する口座の種類です。共に投資利益の管理や確定申告に関わる大切な役割を担っていますが、それぞれの特徴や税金の扱い方は異なります。証券口座を開設する際には、口座の種類を特定口座と一般口座から選ばなければなりませんが、どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。
本記事では、これらの口座の基本的な仕組みや選び方を初心者にもわかりやすく解説していきます。
特定口座と一般口座の違い

株式などの購入や保有、売却には、証券会社で「証券口座」の開設が必要です。まずは特定口座と一般口座の概要を比較し、税金の計算や納税手続きの違いを確認していきましょう。
株式や投資信託で生じる利益には、約20%の税率がかかるのが一般的です。特定口座の場合は必要に応じて証券会社が年間取引をまとめ、源泉徴収を行う形が選べるため、投資家が直接税額を計算する負担を減らすことができます。一方、一般口座では投資家自身が取引記録を管理し、損益を計算して確定申告を行わなくてはなりません。まずはこのような基本的な違いを把握することが大事です。
多くの投資家にとって、税金関連の手間はできるだけ簡素化したい部分といえます。特定口座の源泉徴収制度は、そのニーズを大きくサポートしてくれる仕組みです。ただし、所得合計額が少ない場合に課税を抑えやすい側面を利用したい場合など、一般口座にもメリットがあります。どちらを選ぶかは、投資家の状況や税金計算の手間感に左右されます。
確定申告に慣れていない場合、特定口座を利用することで手続き上のミスを減らすことができます。一方で、一般口座を選ぶことで、投資の損益管理を自分で把握しておきやすくなるという利点などもあります。税金関連の作業量に注目しながら、口座の選択を考えてみるのも一案です。
特定口座とは
特定口座とは、金融機関が利用者の代わりに1年間の損益を計算し、年間取引報告書を作成する口座です。投資で得られる配当金や売却益などにかかる税金の計算を金融機関におまかせできるため、投資家自身の手続き負担を大幅に軽減できます。
また、源泉徴収の有無を選ぶことができ、「源泉徴収あり」を選ぶと、基本的には年度末の確定申告をしなくても納税が完了します。
その一方で、「源泉徴収なし」を選択すれば、利益が出たときは自分で確定申告を行う必要がありますが、特定口座であれば確定申告の際に年間取引報告書の内容を転記すれば良いため、申告の負担が大きく軽減されます。
投資金額が小さいうちは税金関連の煩雑さが気にならないというメリットが大きく、初心者にも扱いやすい制度なため、実際、源泉徴収ありの特定口座でスタートする投資家は多いです。
しかし、投資額や収益が増えてくると、自分で確定申告を行い、他の控除や損益通算を駆使して税金を抑える方法を検討することもあり得ます。
一般口座とは
一般口座とは、取引が成立した際に交付される取引報告書をもとに、利用者が自分で1年間の損益を計算する口座です。金融機関から取引報告書が定期的に出るものの、それを使って年間を通じた売買履歴を自分でまとめ、税金の計算を行う手間が発生します。
投資利益だけでなく、配当金や譲渡損益の状態も自ら把握しながら申告書類を作成することが重要となり、確定申告の準備を自分で行う必要があります。
手間をかける分、個別の事情に合わせて最適な税額計算を行えるのが一般口座のメリットです。例えば、所得額が一定基準を下回る場合には課税額を抑えられる可能性があり、扶養内で投資を行いたい方や学生の方などが活用すると大きな効果を得られることがあります。
逆に、日頃からの記録管理や確定申告の知識が欠かせないため、投資に慣れている方や経験者向けといえるでしょう。年間取引報告書を作成し、総合課税や分離課税などどの方式で申告するかを決める必要もあります。損益が複数の証券会社にまたがる場合は合算も必要で、煩雑になるケースも多いです。
結果として、初心者にはややハードルが高いと感じられるかもしれません。しかし、将来的には一般口座での運用に慣れることで、投資全体の把握がしやすくなる面もあります。
特定口座の種類
証券会社が年間取引報告書を作成する特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。それぞれの違いを解説します。
源泉徴収ありの特定口座
「源泉徴収あり」の特定口座では、売買益や配当金を得た時点で自動的に税金が差し引かれます。原則自身による確定申告の必要がないため、投資初心者がはじめに選ぶ選択肢になるケースが多いです。
また、会社員のように給与所得がある場合、投資利益を会社や家族に知られにくい利点もあります。取引の都度損益を計算して源泉徴収もしくは還付が行われるため、原則確定申告の必要もありません。
源泉徴収なしの特定口座
「源泉徴収なし」の特定口座では源泉徴収を行わないため、売却益が出た場合に税金は引かれません。取引ごとの集計は証券会社に任せつつ、最終的な納税は自分で行う形式です。投資利益が少額な段階であれば、源泉徴収による課税を抑えられ、結果的に負担を軽くできる場合があります。自分で損失繰越や各種控除をうまく活用できる方には特に向いている選択肢です。
ただし、一般口座同様に確定申告の準備は必要になります。「源泉徴収あり」よりは自由度が高い反面、税金の手続きに対して一定の理解が不可欠となります。損益通算をきちんと行うことで、前年度の損失を翌年以降に繰り越して節税効果を得るなど、自分の状況に合わせた工夫ができる人には魅力的な選択肢です。
そのため、自分で確定申告をする必要があります。一般口座と比較すると、損益の計算は金融機関が行うため、確定申告時には年間取引報告書の数値を転記するだけで良く、簡単に済ませられる点はメリットです。
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしたほうが良いケース

特定口座(源泉徴収あり)は、金融機関が納税までを代行するため、原則確定申告は不要です。しかし、会社員でも年収2,000万円超の人や、副業収入が一定以上ある場合は別途申告が必要になる場合があります。
医療費控除や住宅ローン控除の適用など確定申告を行うタイミングで、投資の損益も合わせて申告するケースも少なくありません。個々の事情によっては、「源泉徴収あり」でも確定申告をしたほうが有利になるケースもあります。
確定申告をしたほうが良いのは、損失が出ているケースなどです。
損失が発生している場合、確定申告をすることで翌年以降3年にわたり損失を繰り越せる「上場株式等の譲渡損失の金額の繰越控除」が適用できます。翌年以降3年間の利益から損失分を相殺できるため、結果的に支払う税金を減らすことが可能です。
例えば今年の損益が20万円の損失の場合、翌年30万円の利益が出ても、繰越控除を適用することで差額の10万円のみが課税の対象となります。これにより、今年の損失を翌年以降の利益と相殺できるメリットがあります。なお、損失の繰越控除を利用する場合には取引がなかった年にも確定申告が必要です。詳細は税務署や専門家に確認すると安心です。
特定口座(源泉徴収あり・なし)と一般口座、どれを選ぶべき?

投資スタイルや状況に応じて、どの口座を選ぶか判断するポイントを整理します。
口座選択のポイントとしては、まず投資家自身の納税意識や知識量が重要です。手続きを簡単に済ませたい場合や、投資に費やす時間をできるだけ減らしたいという方は、源泉徴収ありの特定口座が無難でしょう。
一方、自分で損益の計算を行うことに抵抗がなく、所得状況に応じて最適化を図りたい方は、一般口座や源泉徴収なしの特定口座を検討する価値があります。
収入の多寡や、投資で得られる利益をどのようにコントロールしたいかも考慮が必要になります。他の収入と合算しながら最適な税金を計算したい場合には、一般口座や源泉徴収なしの特定口座を選ぶことでメリットを得られるかもしれません。
また、一般口座や源泉徴収なしの特定口座は源泉徴収ありの特定口座よりも資金効率が有利なる可能性もあります。源泉徴収ありの特定口座では利益が発生すると、20.315%の税金が引かれますが、一般口座や源泉徴収なしでは税金がすぐに引かれることはありません。
「一般口座」や「源泉徴収なし」を選べば納税は翌年になるため、税金分の額を再投資することで、効率的な運用が可能になり得ます。なお、特定口座での受け入れができない商品は、一般口座での取引が必要です。例えば、未公開株式の取引や、外国株でのスピンオフ受け入れなどが該当します。このような取引を行う場合は、一般口座を使用しなければならないことを覚えておきましょう。
自身のライフステージや投資額の増減に合わせ、最適な選び方を見つけていくことが大切です。
まとめ
特定口座と一般口座の違いは、年間の損益を証券会社が計算するか、利用者自身が計算しなければならないかです。特定口座は税金関連の負担を軽減し、「源泉徴収あり」であれば確定申告を不要にできる点で投資初心者から高い支持を受けています。「源泉徴収なし」であれば微調整がしやすい反面、確定申告の準備が必要です。
一般口座は、投資家が自分で年間取引報告書を作成する必要があり、その分税金の計算を細かくコントロールできるメリットがあります。ただし、知識や手間がかかるため、初心者のうちは敬遠されがちです。一方で所得が少ない方や、特定の控除をスマートに活用したい方には向いています。一般的には特定口座を選ぶのが便利ですが、未公開株など特定口座が利用できない取引については、一般口座を利用する必要があります。
口座の選択前には、現在の年収や投資規模、将来どのように投資を拡大したいかなどを踏まえて検討することが大切です。実際に投資を始めてみてから口座種別を変更することも視野に入れると良いでしょう。自身の投資スタイルに合った口座を選んで、長期的な資産形成をスムーズに進めてください。
ご留意事項
免責事項
本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。