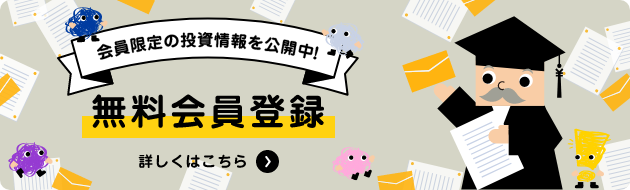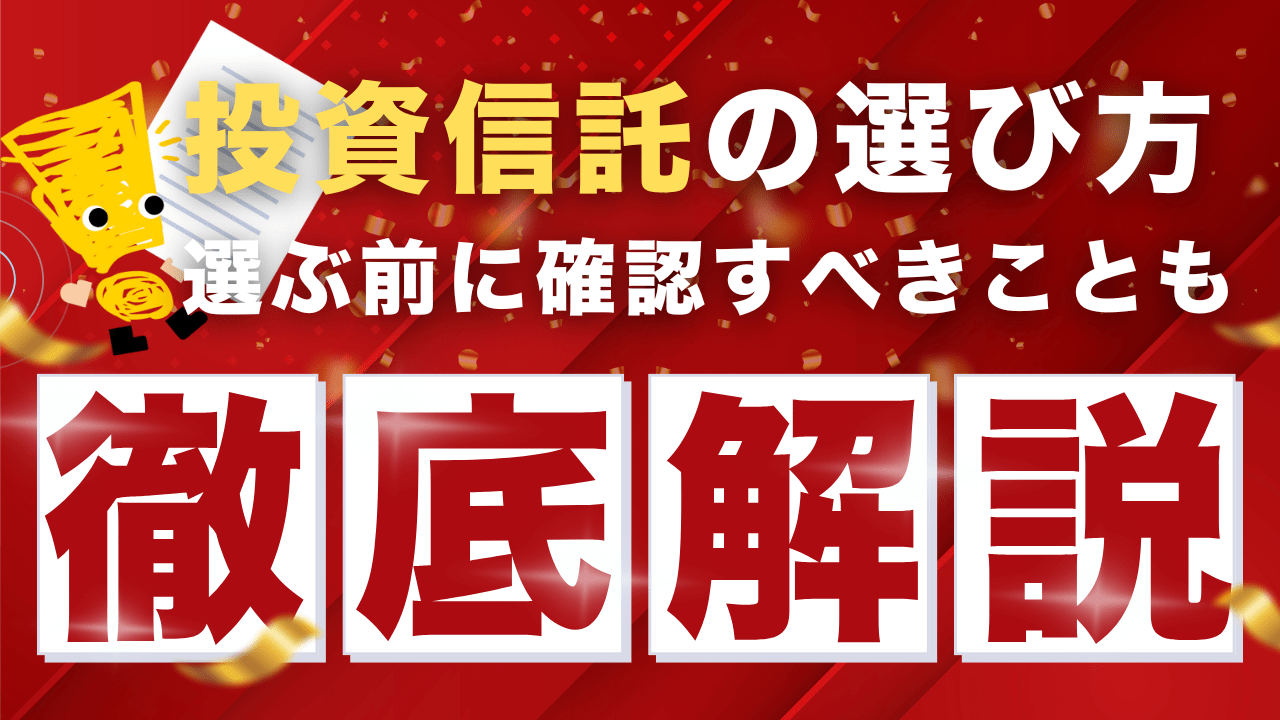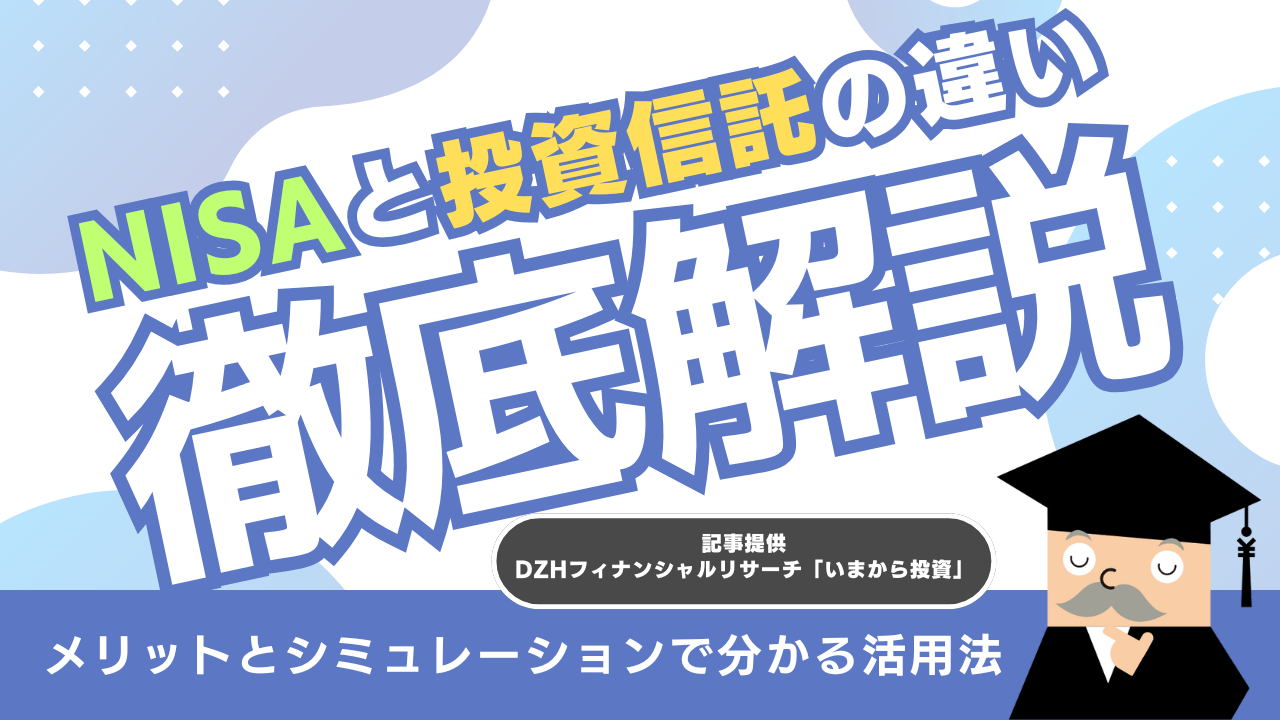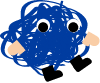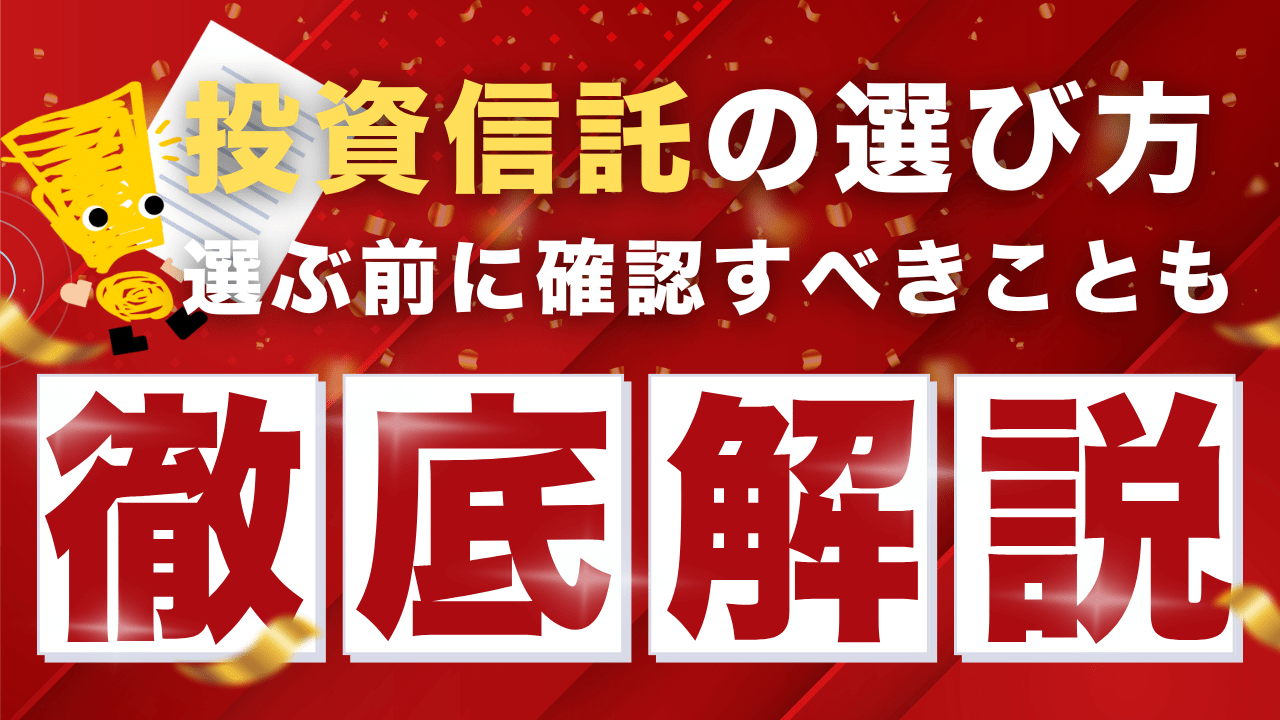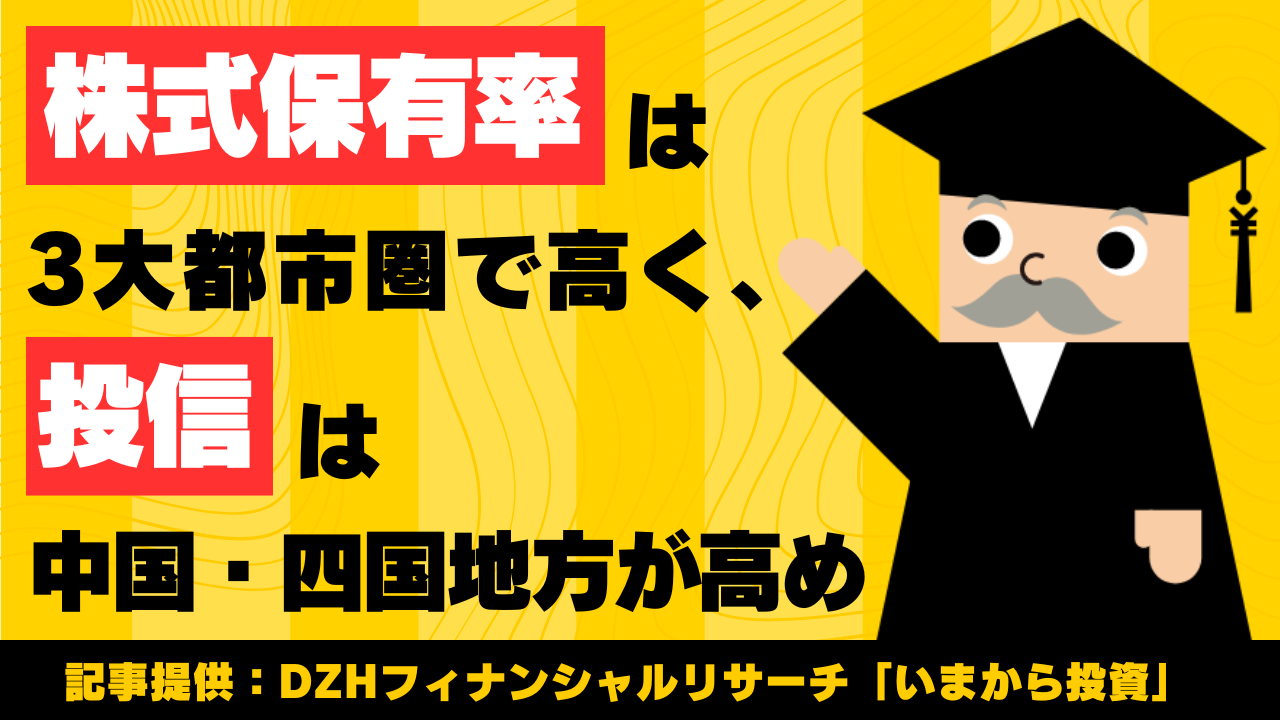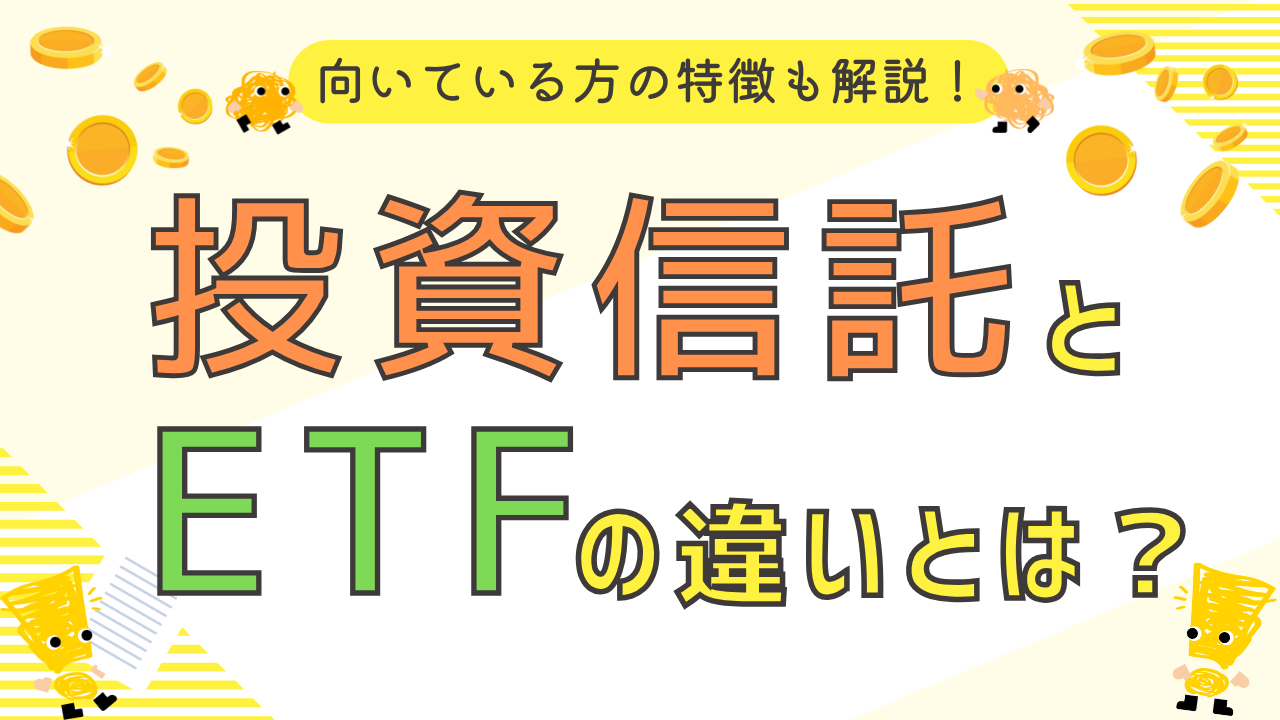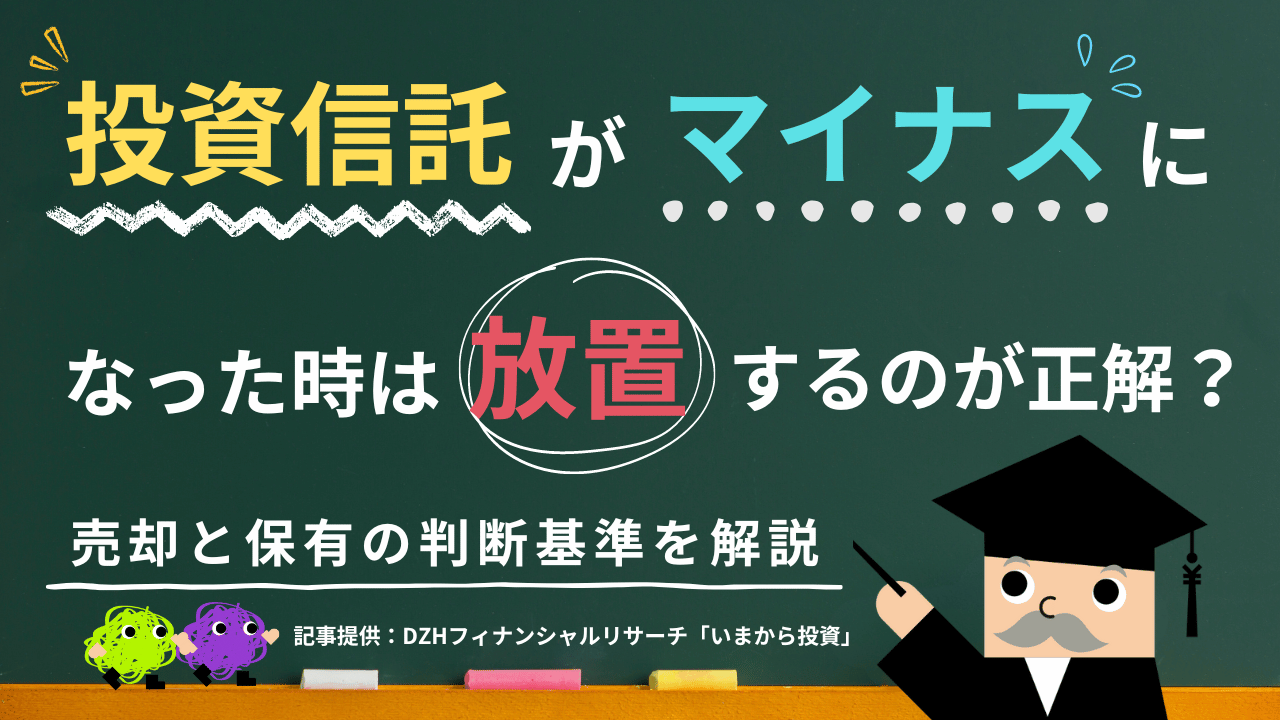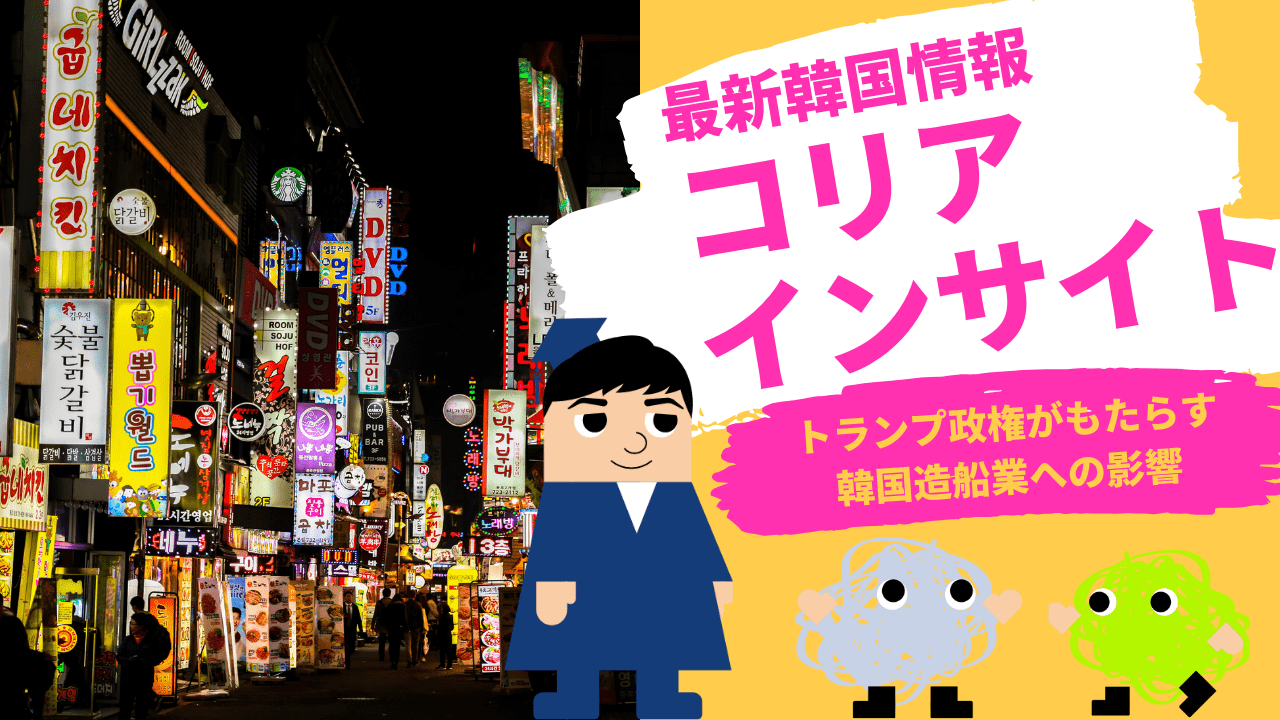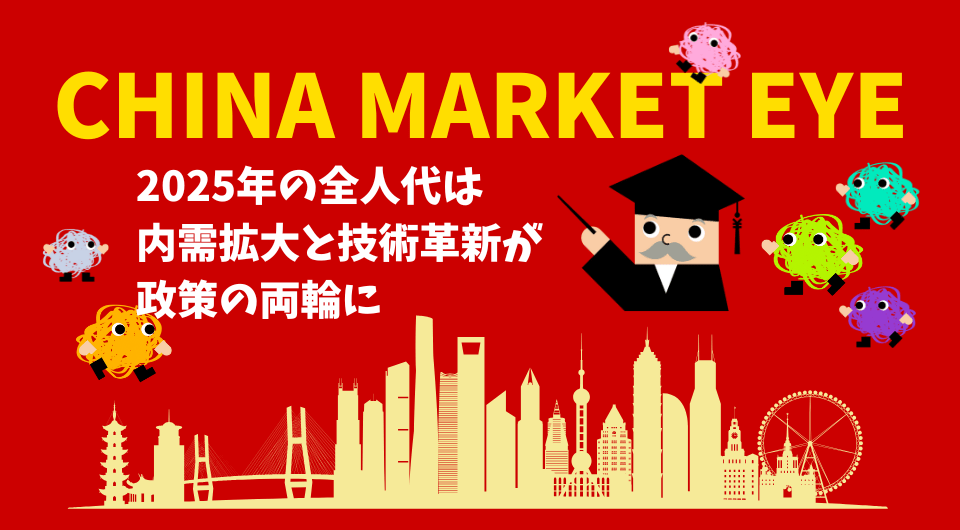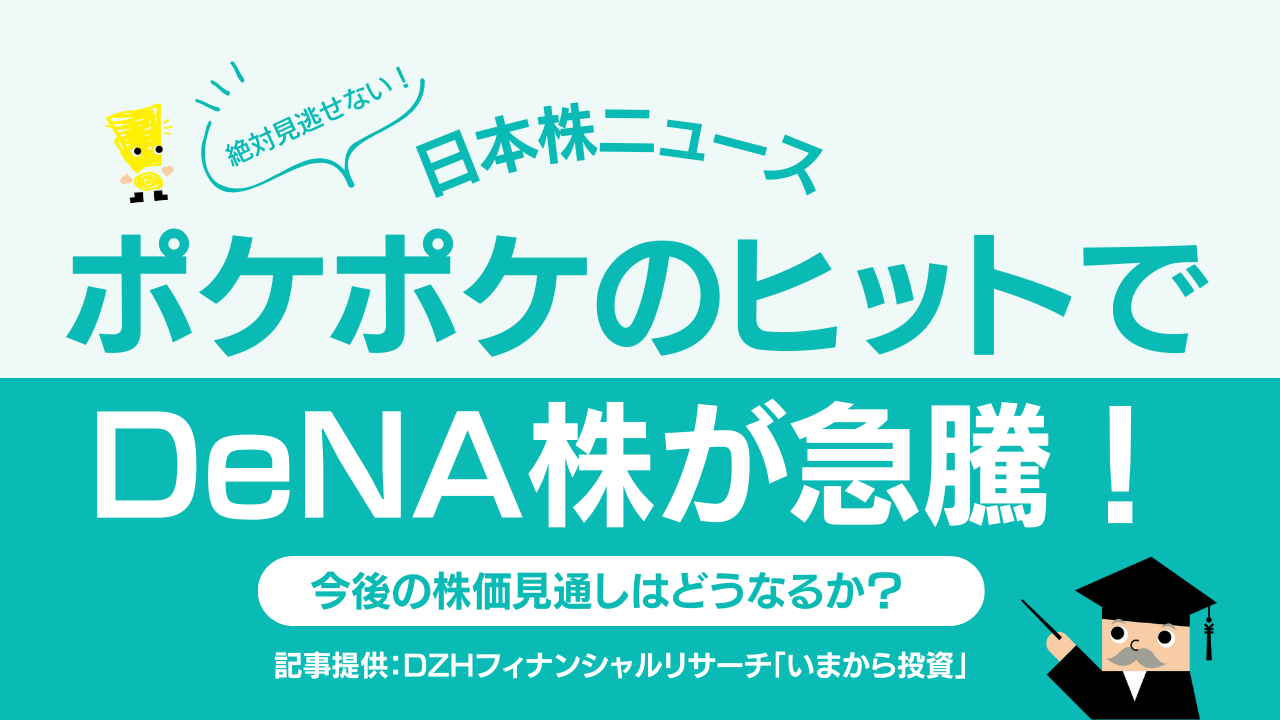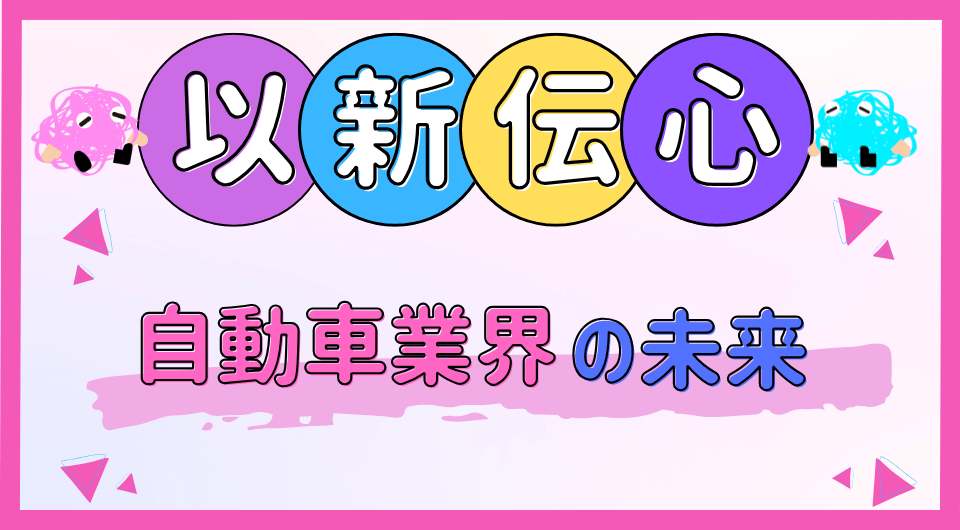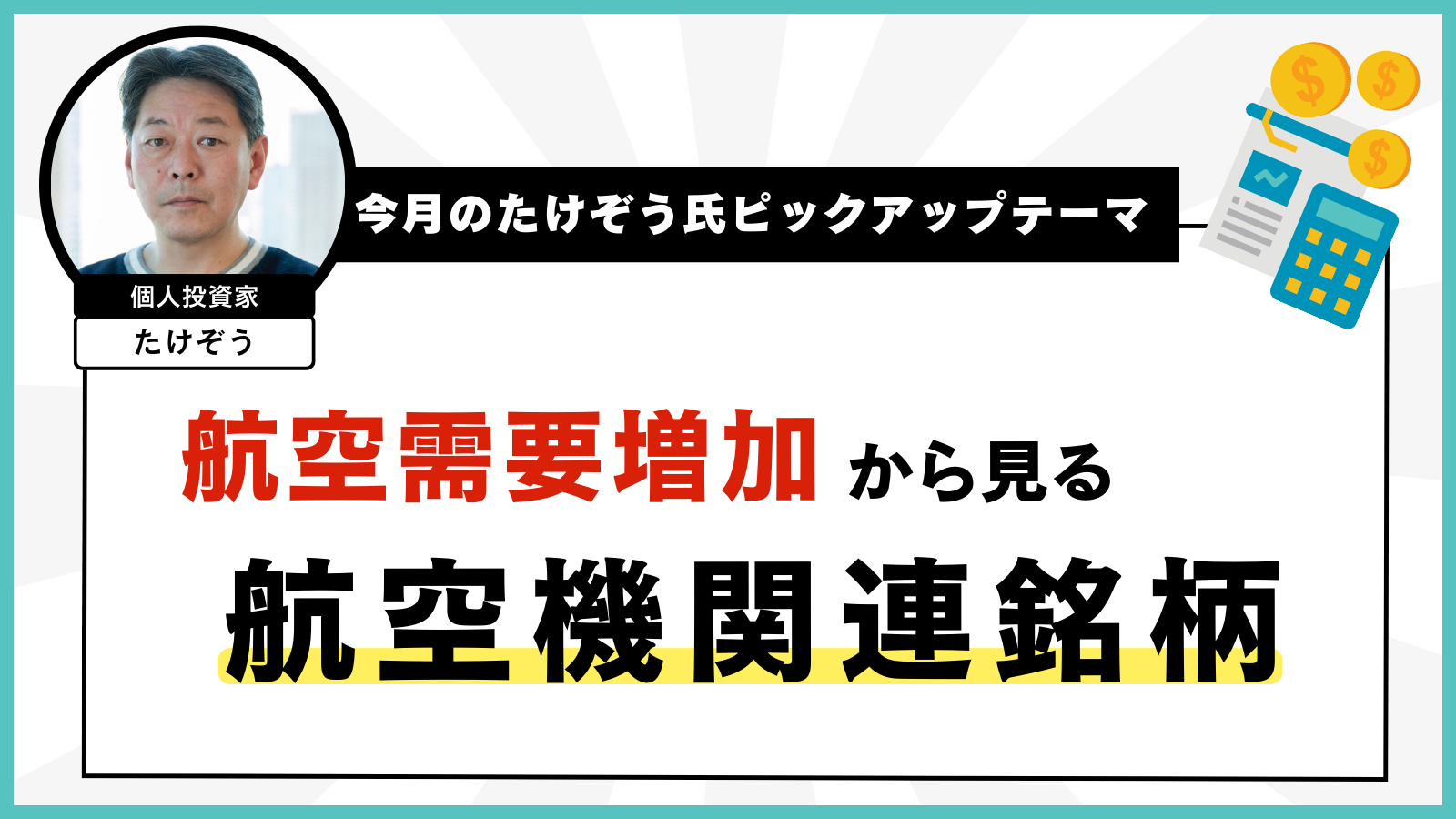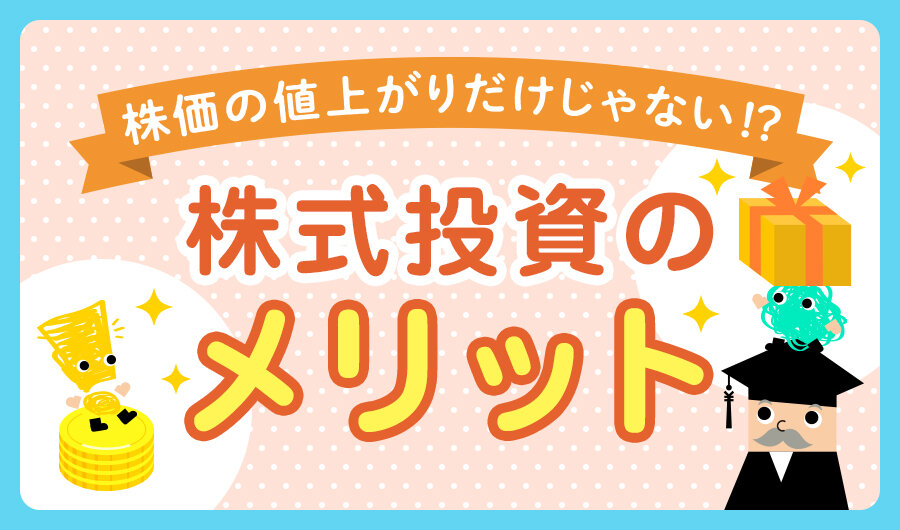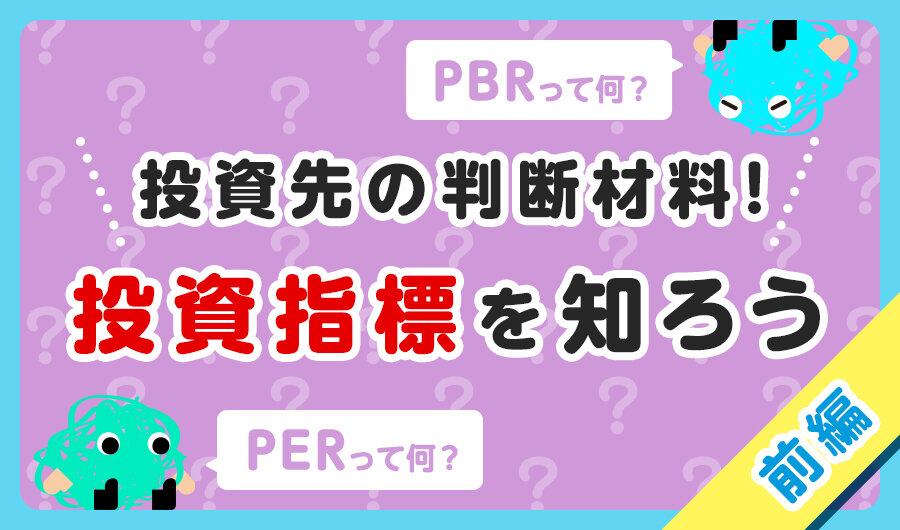投資信託の基準価額とは?価額を左右する要因から算出方法まで解説
2025.04.03 (木)
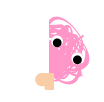
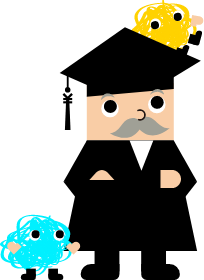

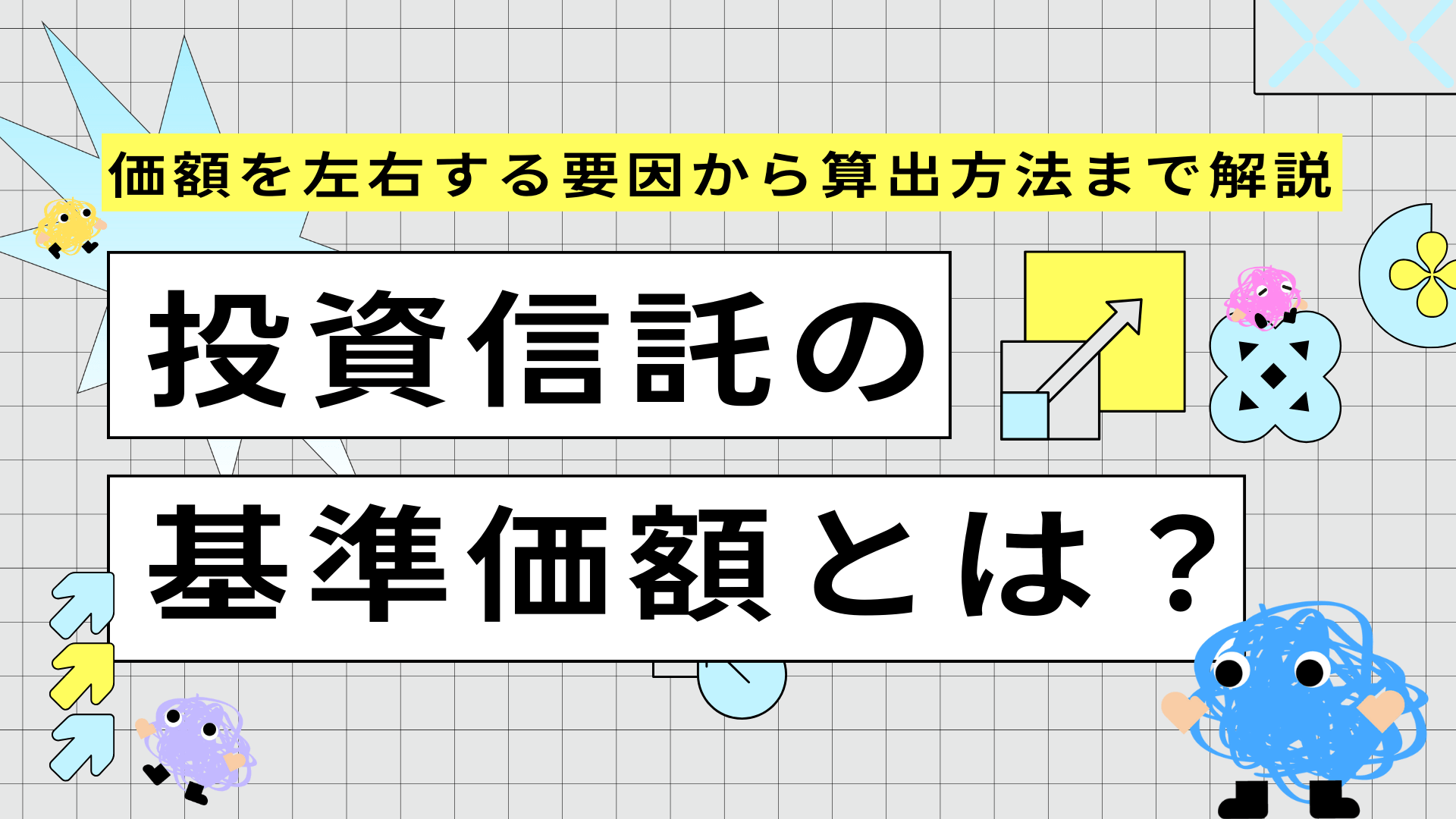
基準価額は、投資信託取引の基準となる重要な指標です。投資信託の取引や運用の際には、基準価額の算出方法や変動要因について理解しておく必要があります。今回は、投資信託の基準価額について詳しく解説します。
投資信託の基準価額とは?

投資信託の基準価額とは、投資信託を取引する際に基準となる、1口または1万口あたりの値段のことです。一般的には1万口あたりの価格とされることが多くなっています。なお、口とは投資信託の取引単位です。基準価額は、ファンドの運用成果に応じて日々変動します。購入時と換金時の基準価額の差が、投資家の損益となります。
投資信託の基準価額は、あくまでも取引の際の価格です。ファンドは商品によってそれぞれ投資対象や分配方針が異なるため、基準価額が高額なファンドが優れている、値上がりが期待できる、というわけではありません。
基準価額の算出方法
投資信託の基準価額は、下記での式で計算します。
基準価額=純資産総額÷総口数
純資産総額とは、投資信託の運用資産のうち、投資家に帰属する額のことで、運用資産の時価総額に利息や配当金などを加えた額から、運用コストを差し引いた金額のことです。純資産総額を総口数で割ることで、1口あたりの価額を算出できます。1万口あたりの値段を基準価額とするファンドであれば、これを1万倍したものが基準価額になります。
基準価額は資産価値を表したものであり、市場での需給バランスで決定する価格とは異なることを覚えておきましょう。
【豆知識】基準価額は1日に1回公表される

一般的な投資信託の基準価額は、投資信託に組み込まれている株式や債券などの時価評価を基に算出され、運用会社によって異なるものの、一般的には1日に1つの価額として公表されます。
投資信託の購入や換金には、この基準価額を用います。
基準価額は、投資信託の取引申込を締め切った後に公表されるため、投資家は当日の価額がわからない状況で取引するブラインド方式での取引となります。これは、基準価額が事前にわかることで、既存の投資家の利益が損なわれるのを防ぐためです。
基準価額を左右する要因
投資信託の基準価額は、投資成果を反映するため、日々変動します。基準価額を左右する要因には、大きく3つがあります。
投資先の価格変動
基準価額は、組み入れている債券や株式などの投資先の時価評価額に応じて変動するのが特徴です。組入資産が値上がりすれば基準価額も上昇し、値下がりすれば基準価額も下がります。
海外の資産に投資している投資信託は為替の変動も基準価額の変動要因になります。投資先の国の通貨に対し円安になれば基準価額は上昇し、円高になれば基準価額は下落します。
分配金支払い
投資信託は、運用成果の一部を投資家に分配金として支払います。投資信託の分配金は、純資産総額から差し引かれるため、分配金の支払い後は基準価額が下がります。
投資先からのインカムゲイン
投資信託の組入資産によっては、資産から配当金や利子などのインカムゲインが入ってくることがあります。これらを受け取った場合、ファンドの基準価額が上がります。
信託報酬等の運用管理費の差し引き
投資信託の運用には、管理費用として信託報酬を支払わなければなりません。信託報酬は日々基準価額から差し引かれています。
また、公正性を保つために監査が義務付けられており、その費用(監査報酬)は決算時に純資産総額から控除され、投資家が間接的に負担する仕組みです。
さらに、株式などの売買時に発生する売買委託手数料も、その都度純資産総額から差し引かれるため、基準価額が下がります。
【投資信託の評価】基準価額以外でチェックすべきポイント

投資信託には、基準価額以外にもさまざまな指標や項目があります。取引にあたりチェックすべきポイントを紹介します。
投資信託の種類
投資信託は、投資対象によってリスク・リターンが異なります。投資対象資産の種類には、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内REIT(国内不動産)、海外REIT(海外不動産)、金などがあり、それぞれ値動きが異なるため、投資成果にも差が出ます。一般的には、国外よりも国内が、株式よりも債券を組み込んだファンドのほうが、リスクを抑えた運用が可能です。
投資信託を選ぶ際には、どのような運用がなされる投資信託なのか、運用目的に合い、投資目的に合った運用成果を期待できるかを確認しましょう。
運用方針や運用成果は、「投資信託説明書(目論見書)」や投資信託委託会社が発行する「月次レポート」「販売用資料」などで確認できます。
純資産総額
「純資産総額」とは、投資信託が運用している株式や債券などの時価評価額の総額に、利息や配当金などのその他の収入を加え、そこから運用費用などを差し引いた金額のことです。
純資産総額の大きな投資信託は、人気があり多くの資金が集まっているということです。一方、純資産総額が小さな投資信託は、大口の解約があれば、払い戻しのために運用資産を切り崩さなければならなくなります。その結果、運用を続けられなくなり、繰上償還になるリスクが生じます。
基本的には、純資産総額が大きく上昇を続けているファンドのほうが、信頼性が高い(繰上償還になるリスクが小さい)といえます。ファンドを選ぶ際には、ファンドの規模も確認しましょう。
騰落率
騰落率は、一定期間において基準価額がどれだけ変動したかを表す指標で、パーセンテージで表されます。過去の運用成績を簡単に把握するのに便利です。
ただし、騰落率には投資信託の購入・解約時の費用は考慮されていないため、実際の運用損益とは差があります。また、あくまでの過去の数値であり、予測には用いることができません。
トータルリターン
ファンドの購入から評価時点までの損益を示す指標が、トータルリターンです。下記の式で計算します。
トータルリターン=ファンドの時価評価額(保有口数×基準価額)+受け取った分配金の合計金額-購入時の支払金額(手数料込)
トータルリターンは期間中に発生した分配金を再投資したものとして計算するため、実際の運用成果を反映した数値になります。購入時の費用も含んでいるので、投資成果をより正確に把握することが可能です。運用成績の比較には、トータルリターンが適しています。
信託報酬や申込手数料
投資信託での運用時に発生するコストです。信託報酬は投資信託によって異なり、インデックス型ファンドは低く、アクティブ型ファンドは高い傾向です。申込手数料は、購入時に発生する費用で、同じ投資信託でも販売会社(証券会社や銀行など)によって異なります。
信託報酬はファンドを保有している間はかかり続けるため、保有が長期間になるほど投資家のコスト負担は大きくなります。同様の投資対象を扱うファンドであれば、なるべく信託報酬の低いものが望ましいといえるでしょう。
まとめ
基準価額は、投資信託を取引する際の値段で、運用成果によって変動します。基準価額はファンドの純資産を口数で割った数字であり、基準価額がファンドの優良性を示すわけではありません。ファンドを選ぶ際には基準価額だけでなく、純資産総額やトータルリターン、手数料など、さまざまな指標を確認しましょう。
ご留意事項
免責事項
本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。