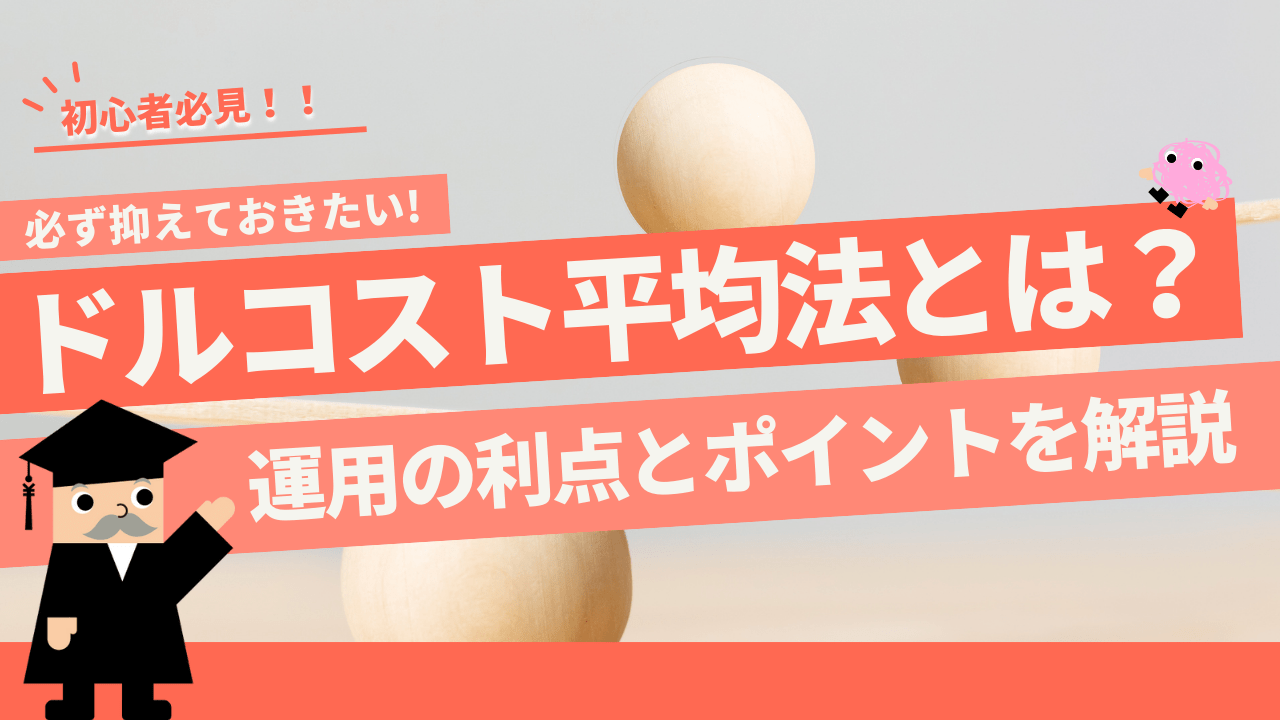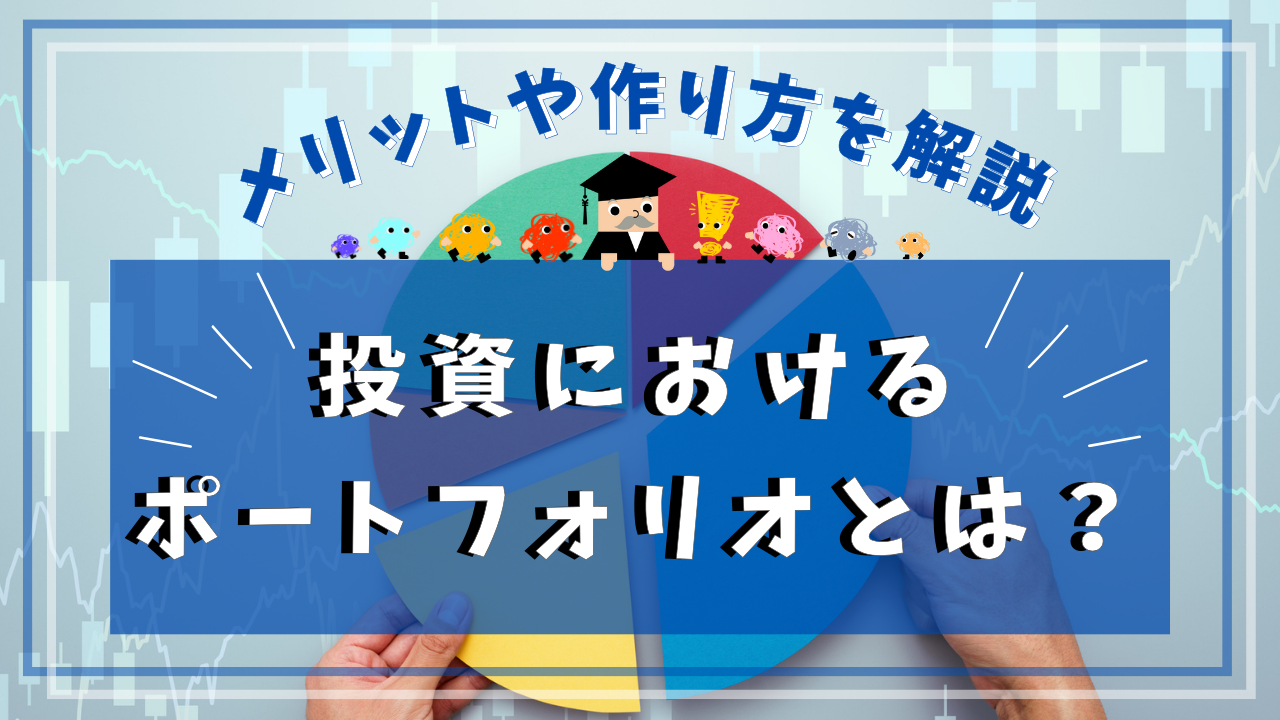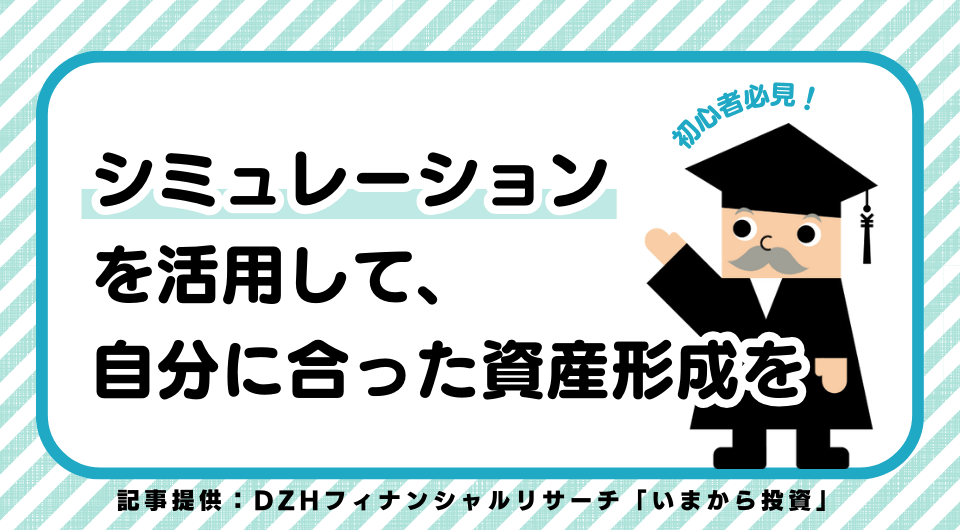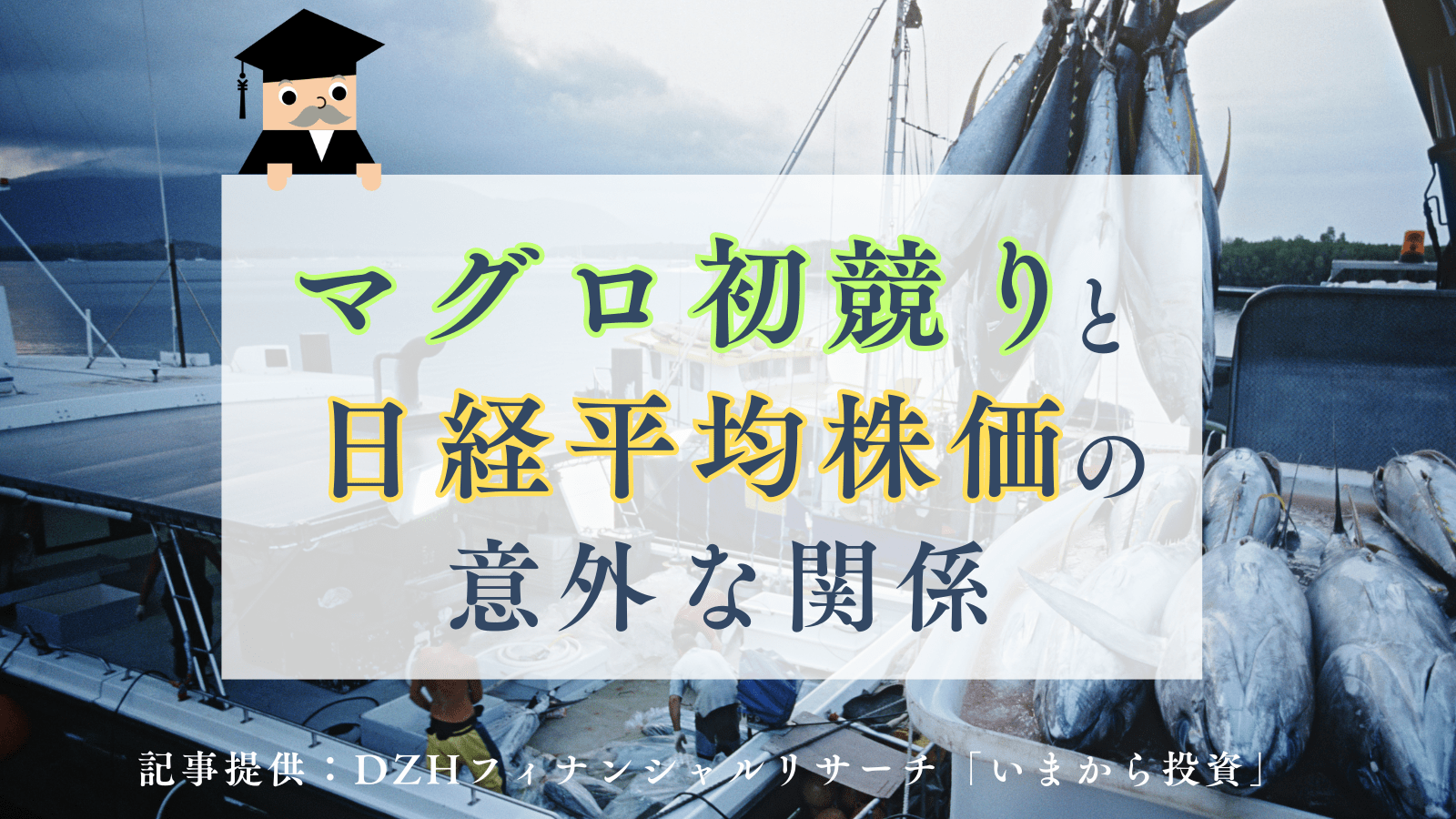上場廃止株は持ち続けるべきか?保有株の売却方法について解説
2025.01.15 (水)



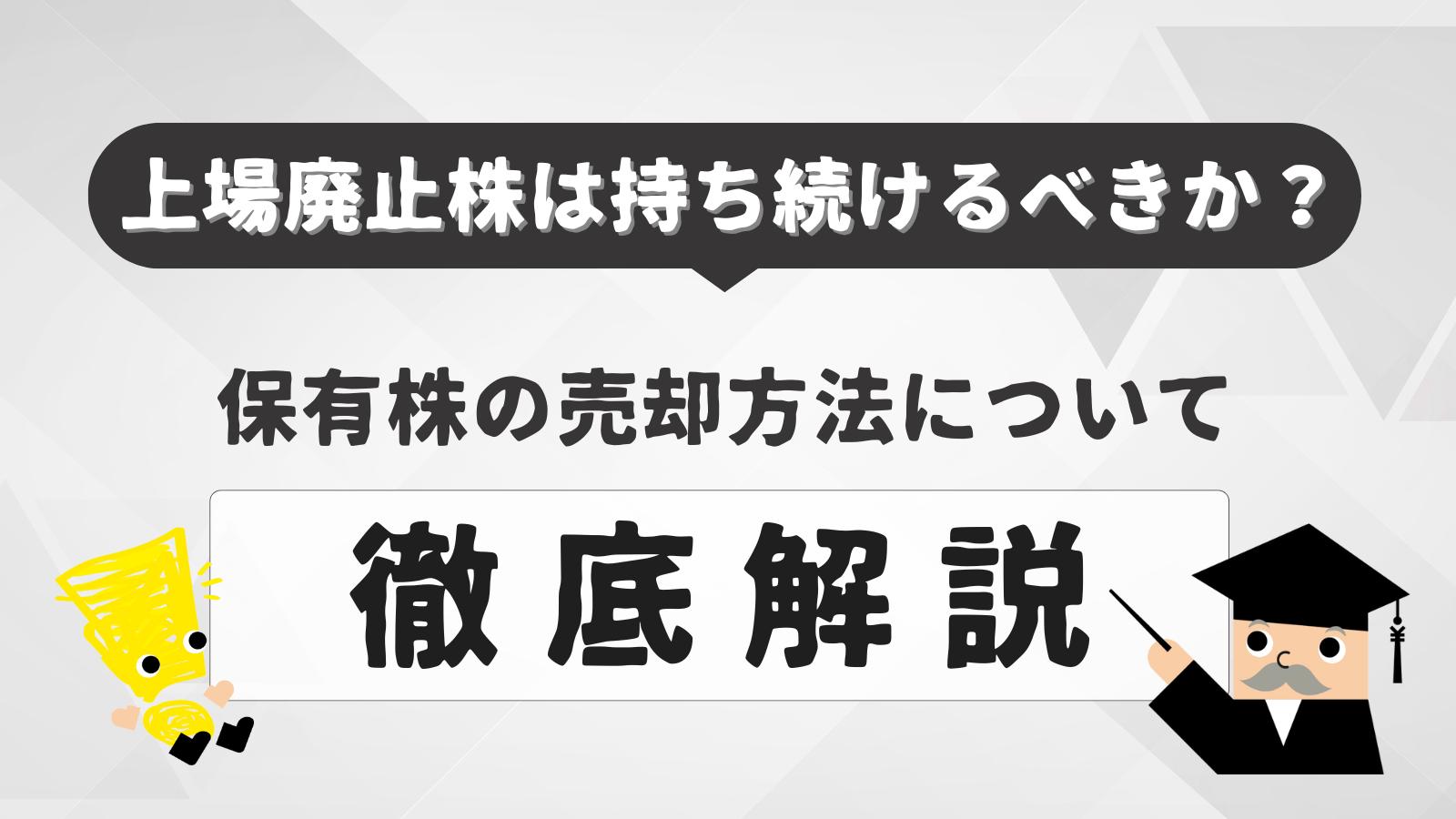
投資を行っているとき、判断に困るのが上場廃止株の扱いです。上場廃止と一口に言っても、その理由はさまざまです。上場廃止と聞いて、まだ株式を保有していたいと思っている方もいれば売却しようか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
今回は、上場廃止が決まった銘柄は持ち続けることができるのか、また保有せず売却するにはどうすればよいか解説します。
上場廃止が決まると株はどうなる?

企業の上場廃止とは、取引所での株式の売買そのものが廃止されることです。企業自身が何かしらの理由で申請するほか、上場廃止基準に該当するなどの理由で株式が上場廃止となることがあります。上場廃止基準に該当した場合、まずは監理銘柄、整理銘柄の指定を受け、最終的には、取引所の判断をもって上場廃止が決定する仕組みです。
まずは監理銘柄、整理銘柄がそれぞれどのような状態なのか解説します。
監理銘柄とは
監理銘柄は、投資する人々が株式の上場廃止に備えられるように周知するための制度です。主に上場廃止基準に該当するおそれのある銘柄や、企業から上場廃止申請を受けて審査期間中にある銘柄を監理銘柄として指定します。
監理銘柄に指定された銘柄は、まだ上場廃止が確定していない状態です。正式に上場廃止が決定する前に監理銘柄として周知することで、投資家は今後の株式の扱いを考えたり後述の整理銘柄の指定に備えたりすることができます。
整理銘柄とは
監理銘柄となった銘柄は、上場廃止が決定すると新たに整理銘柄に指定されます。整理銘柄は、上場廃止基準に該当または企業からの上場廃止申請が正式に受理され、廃止することが決まった銘柄が対象です。原則として上場廃止の1か月前に行われます。
整理銘柄に指定された銘柄は、上場廃止の1か月前から廃止日までの期間のみ、投資者が売買できます。上場廃止日以降になると、該当銘柄の株式は取引市場では売買できなくなるため、注意が必要です。
上場廃止になる理由

企業が上場廃止になる理由は、さまざまです。経営状態の悪化を連想しがちですが、必ずしも経営不振が続く企業のみが上場廃止となるわけではありません。例えば、企業側が経営戦略の一環として、自主的に上場廃止を選択するケースもあげられます。
監理銘柄や整理銘柄に指定されたとしても、廃止の理由によっては投資家に利益が出る場合もあります。該当銘柄を保有する投資家は慌てて手放すのではなく、まずは上場廃止となる理由を確認して手放す時期を検討しましょう。
ここでは、企業が上場廃止となる主な理由を3つ解説します。
経営破綻
1つ目の上場廃止理由は、企業の経営破綻です。経営状態が芳しくなく、利益に対して負債が大きかったり自己資本比率が20%以下となっていたりする場合、経営破綻に陥りやすいといえます。
経営破綻した企業が上場廃止した場合、企業側に返済義務は生じません。保有している株式は価値がなくなり、いわゆる「紙切れ同然」の状態となるおそれがあります。
株式価値がなくなる前に対応できるように、こまめに企業のコーポレートサイトや証券会社で情報収集することが大切です。
上場廃止基準に該当
2つ目は、上場廃止基準に該当した場合です。金融商品取引所は、上場した企業に対して一定の維持基準・上場廃止基準を設けています。下記の上場廃止基準に該当した場合は、上場廃止の候補となります。
・上場維持基準不適合
・有価証券報告書等の提出遅延
・虚偽記載または不適正意見等
・特別注意銘柄等
・上場契約違反等
・破産・再生・更正などの手続き など
上場維持基準は、企業の純資産や時価総額のみならず、株主数や流通株式数、1日の平均売買代金など株式の取引状況も含まれます。上場維持基準を満たせず、金融商品取引所より指摘を受けたときは、原則として1年以内に改善しなくてはなりません。期限内に改善できなかった場合は、上場廃止基準に該当すると判断されます。ほかにも有価証券報告書等の提出が遅延したり、記述内容に虚偽があったりした場合や違反行為があった場合なども、上場廃止となることがあります。
内部管理体制に問題があった場合も特別注意銘柄に指定されるおそれがあるため、早急な改善が必要です。
経営戦略
3つ目は、経営戦略の一環で企業が自主的に上場廃止を申請しているケースです。
前向きな理由で企業が上場廃止するときは、MBOを行っている可能性が考えられます。MBOとはマネジメント・バイアウトの略称で、他の投資家と協力して企業の経営陣が自社株を買い取ることです。
上場を維持するためには、前述の上場維持基準を満たさなくてはなりません。上場維持は、株主への配当金支払いなどコストもかかります。上場廃止すれば上場維持にかかるコストを削減できる上、株主の意見に左右されず経営できます。
MBOによる自主的な上場廃止は、企業の経営力を強化させることが狙いです。ある意味M&A的な要素が強いともいえます。
上場廃止が決まった株はどうしたら良い?

上場廃止になりそうな銘柄を保有している場合、次の行動としていくつかの選択肢があります。ここでは、上場廃止が決まった株式の扱いに困ったとき、どのような行動をとるべきか解説します。
株式公開買付けに応じる
上場廃止が決定すると、取引所外で企業による株式公開買付け(TOB)が実施されます。しかし、公開買付けには必ずしも応じる義務はありません。TOBの特徴は、プレミアが付与されることです。買付けに応じれば、通常よりも高値で売却できる可能性があります。
また、TOBに応じる場合は、売却にかかる手数料は無料となっている証券会社がほとんどです。無料で株式を手放せる点もTOBのメリットといえます。
提示された株価と自分が保有している株価を比較し、利益を考慮したうえで最終判断を下しましょう。
信託銀行で金銭交付を受ける
上場廃止が決定した銘柄は廃止日までは保有が可能です。もしTOBに応じなかった場合は、信託銀行によって金銭交付を受ける対象となります。
この場合の注意点は、金銭交付を受けても損益通算に反映できないことや別途確定申告が必要となる可能性も発生するということです。加えて、金銭が支払われるのは、株式上場廃止の2~3か月後となるので、手元に届くまで時間がかかります。
市場で売却する
前述した通り、上場廃止が決定した銘柄は整理銘柄として指定されます。整理銘柄に指定される時期は、一般的に上場廃止の1か月前です。整理銘柄に指定されている期間中であれば、単元株の場合通常通り取引市場で売却できます。
しかし整理銘柄の期間を過ぎれば売却できなくなるので、タイムリミットに注意しましょう。
保有し続ける
株式をそのまま上場廃止日まで持ち続ける選択肢もあります。ただし、上場廃止日をすぎると、原則支配株主や該当の発行会社が強制的に取得するため、結果的には手放さなくてはなりません。支配株主などが強制的に株式を取得する場合、保有していた株主には対価(金銭)が支払われます。市場での売買とは異なり、対価の支払いは上場廃止直後ではなく、2~3か月後となります。
まとめ
上場廃止株は、必ずしも企業の経営不振が原因とは限りません。なかには、経営戦略の一環として自主的に株式の上場廃止を申請する企業もあります。
保有している株式の上場廃止が決まったときは、慌てず原因を調べましょう。経営戦略の場合、TOBによりプレミア付きの価格で手放せる可能性が考えられます。
整理銘柄の制度が設けられていることで即座に上場廃止されるわけではないため、保有し続けるかどうか落ち着いて決めることが大切です。
ご留意事項
免責事項
本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。